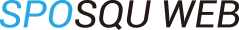生涯学習として老若男女が楽しめる
「おはじきサッカー」を日本の文化に
いま足立区を中心に各地で〝指でおこなうサッカー〟が人気を集め始めています。その名も「おはじきサッカー」。日本では馴染みが薄いものの、25年前からワールドカップが開催されているなど、とくに欧州を中心に世界で人気を集めています。今回は「日本おはじきサッカー協会」の鴻井建三会長に、おはじきサッカーの魅力、協会設立の経緯や活動内容を語っていただきました。(聞き手:谷口敏和/執筆:高橋武男)
――「日本おはじきサッカー協会」を2007年4月に設立されて今年で10年になります。「おはじきサッカー」とはどのようなものなのか、教えてもらっていいでしょうか?

ひと言でいえば、「指でおこなうリアルサッカー」ですね。具体的には、サッカー選手のフィギュアが乗ったおはじきを指で弾き、ボールに当ててゴールを目指すテーブルサッカーゲームです。
フィギュアのサッカー選手が、あたかもボールをドリブルしているかのようにゲームが進んでいくため、テーブルサッカーの中ではサッカーのテイストを最もリアルに再現していると思いますよ。
試合時間は15分×2の合計30分。ビリヤード台のようなミニチュアのサッカーコートの両側にプレーヤーが立ち、ルールに従い攻守が入れ替わりながら一対一で対戦します。人差し指か中指を使っておはじきを弾き、パスやドリブルを繰り出しながらゴールを狙います。
何よりの魅力は、サッカーの戦略性を引き継いでいる点ですね。空間を支配する戦略が求められるので、リアルのサッカーと同じような白熱したゲーム展開が楽しめます。
――お話を伺うととても楽しそうですね。
そうなんです。残念ながら日本では馴染みの薄いゲームですが、おはじきサッカーの起源は古く、サッカーの母国イギリスで70年前に生まれた国際的にポピュラーなゲームです。
とくにヨーロッパでの人気が高く、レゴ社が欧州で実施したアンケートによると、「子どものときに遊んだおもちゃ」の4位にランキングされているほど。世界一を決めるFISTFワールドカップは25年前から開催され、30ヶ国以上が参加しています。
世界的にこれほど人気なのに、なぜ日本で知っている人が少ないのか。主な理由はふたつあると思っています。ひとつは価格です。私たちが協会を設立した10年ほど前にプレーセットの輸入販売を始めたのですが、当時は1万5000円程度と割高でした。現在は6000円程度とかなり入手しやすくなっています。
もうひとつは、プレーが若干難しい点です。加えてルールも少し複雑なので、最初は誰かに教えてもらったほうが上達が早いんです。日本でいえば将棋も最初は難しいですが、親や知人など周りの人から教えてもらえるので自然と覚えていきますよね。
同じように、ヨーロッパでは小さい頃からおはじきサッカーを学べる環境があるため、大人から子どもへと引き継がれていくんです。ですが日本では知っている人が少ないですし、いざ始めようとしても価格的なハードルもある。このように価格と環境がネックとなって日本での普及が立ち遅れてきたと考えています。
――そうした日本の状況のなか、鴻井さんはどのようなきっかけでおはじきサッカーと出合い、協会を設立されたのでしょう。

作業療法士でもある私はいまから10年ほど前にハンドセラピストとして働いていました。最初はおはじきを使ったリハビリを行っていたのですが、サッカーが好きだったこともあって、サッカー関連のリハビリグッズを探す中でおはじきサッカーにたどり着いたんです。
おはじきサッカーは指を使うのでリハビリに最適であるだけでなく、手先が器用な日本人に向いているゲームだと思いました。
ところが当時、日本にはおはじきサッカーを普及させるための組織がありませんでした。そこで、ゲームを日本に広く浸透させたいという思いで協会を設立することにしたのです。
おはじきサッカーの国際組織FISTF(フィスティフ)に連絡して協会設立の許可をもらい、2007年4月、鈴木康弘とふたりで「日本おはじきサッカー協会(Subbuteo Japan)」を設立しました。
ちなみに、おはじきサッカーは世界では「SUBBUTEO(サブティオ)」という名称で知られています。日本では聞き慣れないことから、私たちが協会を設立する際に「おはじきサッカー」という日本の名称をつくりました。

――協会の活動を軌道に乗せるのは大変だったのでは?
おっしゃる通りで、設立してから2011年頃までは、実質私ひとりでほとんどの活動を行っていたこともあって大変でしたね。
協会としてまず取り組んだのは、正式ルールの和訳です。特有の用語もあることから苦労しました。2009年には横浜で日本初のFISTF公認大会を開催。当時、日本には公式選手がいなかったことから、海外から選手を招待して大会の実現にこぎつけました。
おはじきサッカーが次第に認知され始めたのは2011年頃です。日経新聞におはじきサッカーを取り上げていただいたのを機に取材を受ける機会が増え、注目を集めるようになりました。
――日本おはじきサッカー協会の具体的な活動内容を教えてください。
2014年頃から協会の活動が徐々に軌道に乗り始めたことから、2015年8月に一般社団法人に移行しました。そして法人化を機に「公共の福祉に寄与する」という事業ビジョン、そして「ワールドカップ優勝」という目標を掲げました。
おはじきサッカーを日本に普及させるために必要なのは、地域に根づかせることだと思っています。そのために各地域にクラブをつくり、地域で選手と指導者を育てる仕組みを整えたうえ、地域対抗トーナメントの開催によって全体の競技力向上につながるような展開を図っています。
さらに地域トーナメントの上位大会として、FISTF公認大会やアジア杯、日本選手権といった各種の大会を開催することで、クラブや選手たちが高い目標を持って競い合える環境を整えています。
そのほか2016年には、Jリーグ東京ヴェルディとのコラボでおはじきサッカー商品を開発・販売し、協会買い取り分を除いて40セットが完売しました。定番商品以外でここまで反響が出たのは、おはじきサッカーの魅力を感じてもらえた証拠だと嬉しく思っています。
また、おはじきサッカーはゲームやスポーツとしての魅力に加え、老若男女が楽しめる生涯学習のツールとしても最適だと考えています。
その可能性を見出してくれたのが足立区の生涯学習センターです。足立区の自治体を上げておはじきサッカーに力を入れ、生涯学習センターにおはじきサッカースタジアムを設置してくれたのです。
さらに足立区の広報がスタジアム設置のプレスリリースを発行し、テレビ局やラジオ局、新聞各紙からの取材を受けて認知が促進されるという好循環サイクルも生まれました。
2017年6月には、この足立区の生涯学習センターでアジアカップを開催することができました。オペラ歌手による国家斉唱を行うなど、会場を盛り上げる工夫も随所に取り入れています。
――最後に今後の目標をお聞かせください。

今後の展望としては、Jリーグへの商品展開という方向性を持ちつつも、同時に子どもが楽しめるゲームとしての可能性を広げていくことです。
全国各地の身近な場所におはじきサッカーを楽しめるピッチがあり、子どもから大人まで、ルールに縛られることなく生涯学習として気軽に楽しめる環境がある――そうやって生涯学習の新たなツール、新たな文化として日本に浸透させていけるよう、今後も普及活動に力を入れていきます。
- SPOSQU WEBの最新情報をお届けします。